恵比寿映像祭とは
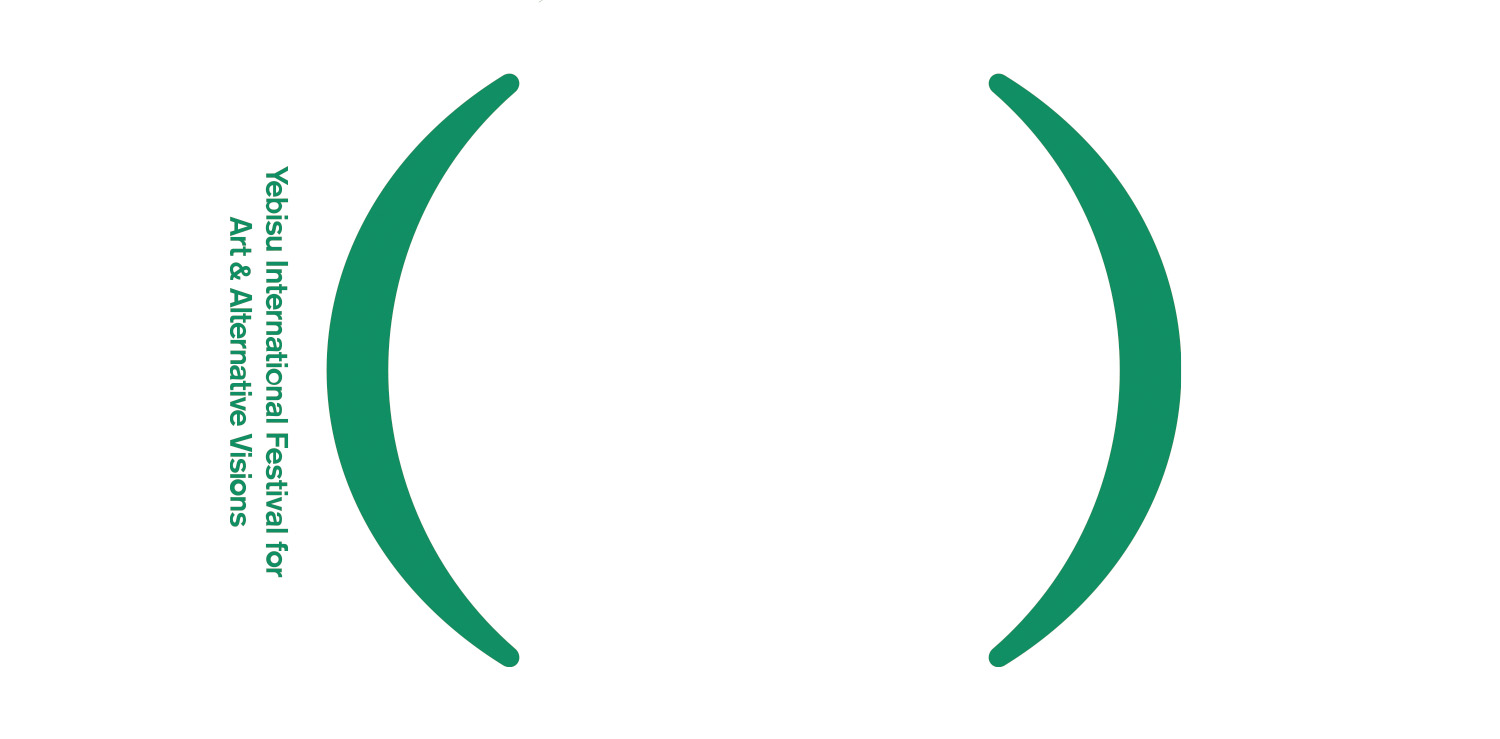
恵比寿映像祭は、平成21(2009)年の第1回開催以来、年に一度恵比寿の地で、展示、上映、ライヴ・パフォーマンス、トーク・セッションなどを複合的に行なってきた映像とアートの国際フェスティヴァルです。映像分野における創造活動の活性化と、映像表現やメディアの発展をいかに育み、継承していくかという課題について広く共有する場となることを目指してきました。
本フェスティヴァルのロゴはそうした背景ももとに、映像をめぐって、ひとつではない答えをみんなで探していこう!という基本姿勢を、オープンなフレームとしてのカッコに託しました。映像というカッコにあえて入れてみることで、はじめて見えてくるものがあるはず――何かを限定するためではなく、いろんなものを出し入れして、よく見てみるためのカッコです。
第14回テーマについて
スペクタクル後|AFTER THE SPECTACLE
誰もが経験したことのないパンデミックによって、私たちの日常は大きく変化しました。その中においても、映像はより身近なメディアとして浸透し、社会、政治、経済、文化の変化を映し出すツールのひとつになっています。とりわけ、ソーシャルメディア上のコミュニケーションによって、誰もが複層的な次元で映像体験が可能となった現代は、祝祭的イヴェントから、災害や戦争などの出来事まで、いかなる情報も、一大スペクタクルに見える時代です。*
スペクタクルという言葉は、風景や光景という意味のほかに、しばしば壮大な見世物という意味で使われています。その語源、ラテン語のspectaculum(スペクタクラム)には、光学的な意味と同時に、地震や火山噴火などの天変地異などが含まれていました。19世紀になると、近代国家の誕生とともに、博覧会、写真、映画のなかで、それまでの天変地異は、壮大な風景や見世物として視覚的に再現され、人々に受容されていきます。
第14回恵比寿映像祭では、「スペクタクル後」をテーマに19~20世紀の博覧会や映画の歴史から現代にいたるイメージおよび映像表現について考察します。現代作家による展示や上映、イヴェントに加え、小原真史氏をゲスト・キュレーターに迎えた博覧会関連資料と当館コレクションによる企画や、映像作家・遠藤麻衣子によるオンライン映画プロジェクト、さまざまな作品との出会いを拡げる教育普及プログラムなどの新たな構成によって、映像体験の可能性を探っていきます。
第14回恵比寿映像祭ディレクター 田坂博子
*フランスの思想家のギー・ドゥボールは1967年に発表した『スペクタクルの社会』で、見世物という限られた意味ではなく、「イメージ」で構成された現代社会を把握する概念として「スペクタクル」を考察し、メディアによってイメージだけを植え付けられ、ただ受け身でいる状態をスペクタクル社会として批判しています。
キーワード
カメラ
ラテン語で「暗い部屋」を意味するカメラ・オブスキュラに由来するカメラは、目に見える風景を光学的に映し出す装置として写真以前に誕生した。写真が誕生した後の19世紀後半以降は、カメラで撮影されたイメージは、博覧会や劇場、映画館のなかで観衆が見る対象として流通していった。西洋における他者としての異民族や異文化のイメージが大衆の好奇心を刺激し人気を博していくのと同時期に、人類学という学問が大きく展開したことは偶然ではない。当時カメラで撮影することは、西洋からその他者へと向けられた植民地的視点から、他者への眼差しを記録する行為だった。鉄道や航路など近代の交通網が整備されると、移動の旅のなかで東方などの異郷が、カメラを通して発見された。それから時代を経た現代でも、カメラで見ること、カメラで撮影することで、他者を理解するのは、決して容易ではない。そしてカメラの像が示す真実は常に定かではない。むしろそこに映し出された見る者の眼差しの先に何があるのかを、写真や映像から想像することに、対話の可能性が残されている。
セルフィー
「セルフィー」(Selfie)は、撮影者自身が被写体となった肖像写真全般を表わす比較的新しい語である。一般的 な使われ方としてはスマートフォンで撮影されSNS上にアップされたセルフポートレイトを指すだろう。肖像写真(ポートレイト)は写真の黎明期、ときに機械的に他者を写し、記録し、科学的に計測・分析する手段でもあった。一方、現代のセルフィーは日記的な用途で撮影されることが多いようだが、同時にSNS上で自己イメージをアピールするための手段としても有効なよう だ。たとえば、フィルター機能で加工し自分の顔を望みどおりに変えることもできれば、日常の特別な瞬間だけを選んで切りとり、SNSのUIに並べることによって、その人の人生全てが輝いているように見せることもできる。 つまりSNS上のセルフィーによって、撮影者自身のイメージを特別な物語に昇華させることもできるのだ。さらにそれを名声へと繋げるには、SNS上のペルソナである「第二の自分」の特別な物語を、ネット上に供給し続けることが必要である。
風景
「スペクタクル」には目をひくような風景という意味も含まれているが、風景という概念の捉え方には時代的にも地域にも偏りがある。ヨーロッパにおいて風景という概念が一般化し、それ自体がイメージとして記録されるようになったのは近代に入ってからで、例えば絵画に描かれる時も、それまではあくまでも人物が描かれるときの背景に過ぎなかった。初期の写真技術であるカロタイプを発明し、世界最古の写真集を発刊したウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットは、その序文の中でカメラ・オブスキュラの映す風景の美しさについて「このような自然の映像をそれ自身の手によって永久に固定し、紙の上に残すことができたらどんなに素晴らしいことか」と感じたことを追憶している。風景を残したい、という人間の欲望が写真の発明にも寄与していたのである。
旅
近代的な交通手段の発達によって人は世界規模で移動するようになり、物資や知識も同様に移動・流通するようになった。17世紀、イギリスを含む欧州圏内では、主に南欧を目的地とする教養としての旅「グランドツアー」が盛んになり、旅行者は体験的に世界を学ぶ契機を得た。旅で目にした風景が人々に与えた影響は大きく、例えばギリシャやイタリアの古代遺跡が18世紀半ばからの新古典主義に、また壮大な自然が19世紀のロマン主義における美や崇高などの観念と結びついた。さらに、19世紀に現れた近代的な映像技術は、旅の体験そのものを持ち運び可能(ポータブル)にした。19世紀末にはリュミエール兄弟が、カメラマンを世界各地に派遣して映像を撮影し、フランスの観客向けに上映した。また、幻燈やシネマトグラフによる上映、音楽の公演などを通じて、無形の文化も伝播し「旅をした」。今日では、国際的なサプライチェーンとインターネットを通じ、人、物、イメージ、文化の世界規模での往来は、日常的なものとなっている。
スペクタクルの社会
フランスの思想家ギー・ドゥボールによる『スペクタクルの社会』(La Société du spectacle)は、ヨーロッパ各地で芸術・文化・社会・政治の統一的批判を行ない、新しい状況の構築を実践した集団、シチュアシオニスト・インターナショナルの理論的集大成として、フランスの五月革命直前の1967年に出版され、現在に至るまで、幅広い哲学的言説および政治的運動に影響を与え続けている。ドゥボールは、現代社会をスペクタクルの概念で分析し、マスメディアや視覚イメージが人間の生活や思想に影響を与え、最終的には大衆を受動的な情報消費者および社会学者のデイヴィッド・リースマンが言う「孤独な群衆」に至らしめる個人の疎外状況を生み出したと考えた。そして、資本主義による共同体のない社会の再構成の結果が、スペクタクル社会であると批判する。断片的な構成による同書は、要約が容易でないが、スペクタクル社会の絶えず変化する性質を分析した点で、19世紀に登場した産業製品の祭典である博覧会から、インターネットやソーシャルメディアなど現代メディアの問題に至るまで、実践的に応用して考察することが可能である。
見世物
珍しい品物や芸を人に見せ、興行化することを見世物と呼ぶ。日本では江戸時代後期から盛んにとなり、主に「曲芸」、「細工見世物」、「動物見世物」といったジャンルに分かれていた。「細工見世物」とは物語や伝説の場面、名所風景などを、各種のからくりやジオラマのような風景画、リアルな生人形などを仕込んで見せるものであった。現在のサーカス、奇術ショー、動物園、遊園地のアトラクションのような要素もあり、庶民の娯楽の対象であった。アトラクションの要素は、リュミエール兄弟やジョルジュ・メリエスらの初期映画の虚構性とも連動し、観客の視覚的好奇心を刺激して快楽を誘う大衆文化への熱狂に繋がっていた。見世物小屋では映画《エレファント・マン》にも登場したフリークショーなどのように生身の人間を展示して見せる場合もあった。人間にしても動物にしても奇異な外見を売り物にしていたが、社会福祉や青少年保護、動物愛護の観点から次第に規制をうけることになり、現在では衰退している。
ヴァナキュラー
建築や写真、民俗学のなかでしばしば使われる言葉で、本来は土地や時代に特有なものを指す。この概念を最初期に提示した例として、建築史家のバーナード・ルドフスキーが1964年にニューヨーク近代美術館で開催した「建築家なしの建築」展があげられる。この展覧会では職業的な建築家の手によるものではない、その土地や風土に根差した独特の建築(例えばイタリアの丘陵地帯を利用した都市や、日本の合掌造りの家など)に注目し関心を集めた。また近年では建築だけではなく、専門家ではない人が作った写真や映像、物語などにもヴァナキュラーなものがあるとして注目し、再評価する傾向がある。ただし何をもってヴァナキュラーとするかという定義は曖昧である。例えば写真の場合はアマチュアが撮った写真だけを指すこともあれば、写真家が自分の作品として発表するもの以外の写真、例えばクライアントが存在する広告写真や風景写真なども含める場合もある。
おばけ
日本語において「おばけ」は変化(へんげ)ともいわれ、自然の存在や現象が既知の様子と異なる姿で認識されたものや、霊など人が感知しえない存在が姿形を伴って現前化したものを指す。その意味を超常的な存在・現象全般にまで広げた場合、おばけは、東西を問わず影絵や幻燈をはじめとする映像コンテンツにしばしば登場した定番のモチーフだと言える。さらに映像の上映自体が超常現象として紹介され、人々に楽しまれた時代もあった。ヨーロッパではキリスト教的でも科学的でもない存在は「見えないものを現出させる」という映像の力によって姿を与えられ、例えば18世紀フランスのファンタスマゴリアではマジック・ランタンを用いて幽霊を現出させた。また東南アジアの現代の映画やソープ・オペラにも、土着のおばけがしばしば登場し、それは時にコミカルな精霊でもあれば、不安定な政情の犠牲者を象徴する場合もある。したがって映像という観点からは、おばけはイノベーションを生み出す原動力でありながらも、非合理なものや、ときに土着的なものへのアクセスという、人々の願望の受け皿であると言える。
アーカイヴ
一般にアーカイヴは、歴史的、文化的価値を基準に、永続的な保存を目的とした記録で構成される。記録がアートにとって重要な役割を持つようになった20世紀は、第一次世界大戦後に台頭したシュルレアリスムなどの前衛芸術に顕著なように、写真や映像をはじめ、メディアを横断した表現を通して既存の近代芸術の枠組が問い直され、各メディアの記録が体系化(ドキュメンテーション)されていった。パフォーマンスの隆盛も、アーティストが自作の記録に向き合う機会を作り出した。1960年代以降のランド・アートやコンセプチュアル・アートの多くで、ドキュメント(写真・映像・テキスト)が重要な役割を担ってきたことも偶然ではない。写真や映像は、近代化の延長線上で、映画や大衆雑誌などの娯楽に寄与しながら芸術としての地位を確立する一方、アーカイヴを形成する記録メディアとしての役割も担ってきた。インターネットやSNSが日常化した時代では、アーカイヴ的思考からの実践が、記憶や記録を通して、見えない人間やモノ同士の対話やネットワークの可能性を広げている。
瞬間
瞬く(またたく)間と書いて瞬間。カメラという機械の眼は、そのわずかな時間を無数に記録してきた。滴り落ちるミルクが作り出す王冠や、大地を駆ける馬の脚が宙を舞う様子など、人間の眼で知覚不可能な瞬間は人々に衝撃を与えた。いまではそうした驚きを撮影してすぐ、SNSで共有することも可能だ。機械の眼から生まれるイメージは以前にも増して日常生活に入り込み、絶え間なく私たちの心を動かしている。ドラムを打ち鳴らすたびに、連動するカメラのシャッターが切られ、さらには繋がったプリンターからそのイメージが出力されるパフォーマンス。写っているのはドラムを叩く本人の姿だ。一瞬のうちに「見る/見られる」一大スペクタクルが繰り広げられる。私たちの日常を思い起こさせるような瞬間が一つひとつ紡がれてゆくスライドショー。アナログのスライドプロジェクターからスクリーンに投映されたイメージは、瞬きをするように切り替わり、残像となって消えてゆく。
見える/見えない
目の前のものを見る。そのとき何かが目に映れば私たちは「見える」と言ってしまう。しかし本当に「見えている」といえるのだろうか。視界に映るものを見た時、ふとした拍子に何かのスイッチが入り、そこに様々な意味や理由を発見し、意識的に「見る」ことではじめて「見える」となる。例えば、同じ被写体をわずかに異なる撮影位置から写した2枚の写真を、ステレオスコープを覗き意識して見てみると急に立体的に見えたり、天井からぶら下がる傘に描かれた鳥が、ストロボが瞬いたとたんに生き生きと飛んで見えたりする。あるいは、視覚障害者を含む多様な人々とともに鑑賞することで「見える」ということの意味を改めて考えたり、古い集合写真が、テーマに気づいたときまったく違う意味を持ち始めたりすることもあるだろう。複数人で同じものを見ても「見える」と「見えない」のスイッチの入るタイミングはそれぞれ異なる。そして見ていても見えないことがあり、わからないことがあるという事実に思い至るだろう。
開催概要
- 名称
- 第14回恵比寿映像祭「スペクタクル後 AFTER THE SPECTACLE」
- 会期
- 令和4年2月4日(金)~2月20日(日)《15日間》月曜休館
- 会場
- 東京都写真美術館、恵比寿ガーデンプレイス センター広場、地域連携各所ほか
- 時間
- 10:00~20:00 (最終日は18:00)※入館は閉館の30分前まで
- 料金
- 入場無料
- ※3階展示室、定員制のプログラム(上映、イヴェントなど)、一部のオンラインプログラムは有料
※オンラインによる 日時指定予約を推奨いたします。
※諸般の事情により、開館時期・内容等を変更する場合がございます。展覧会等 の詳細、最新の情報は映像祭ホームページをご確認ください。
- 主催
- 東京都/公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術館・ アーツカウンシル東京/日本経済新聞社
- 共催
- サッポロ不動産開発株式会社/公益財団法人日仏会館
- 後援
- 株式会社TBSホールディングス/J-WAVE 81.3FM
- 協賛
- サッポロビール株式会社/東京都写真美術館支援会員
スタッフ
- ディレクター
- 田坂博子
- キュレーター
- 多田かおり、伊藤貴弘、遠藤みゆき、藤村里美
- エデューケータ―
- 武内厚子
- インターン
- 丹治圭蔵、戸部瑛理
- 広報・渉外・地域連携
- 池田良子、平澤綾乃、鈴木彩子
- プロデューサー
- 柳生みゆき
- 学芸統括
- 関次和子
- ゲスト・キュレーター
- 小原真史
- 編集
- 内田伸一
- 和文英訳
- アンドレアス・シュトゥールマン、中野勉、ジャン・ユンカーマン
- ウエブ・デザイン
- 前田晃伸、黒木晃、庄野祐輔(MAEDA DESIGN LLC.)
- CG
- 浮舌大輔
- ウエブ監修
- 萩原俊矢

