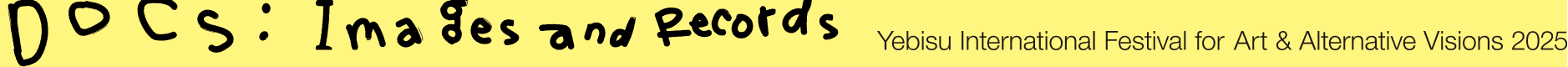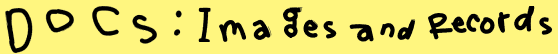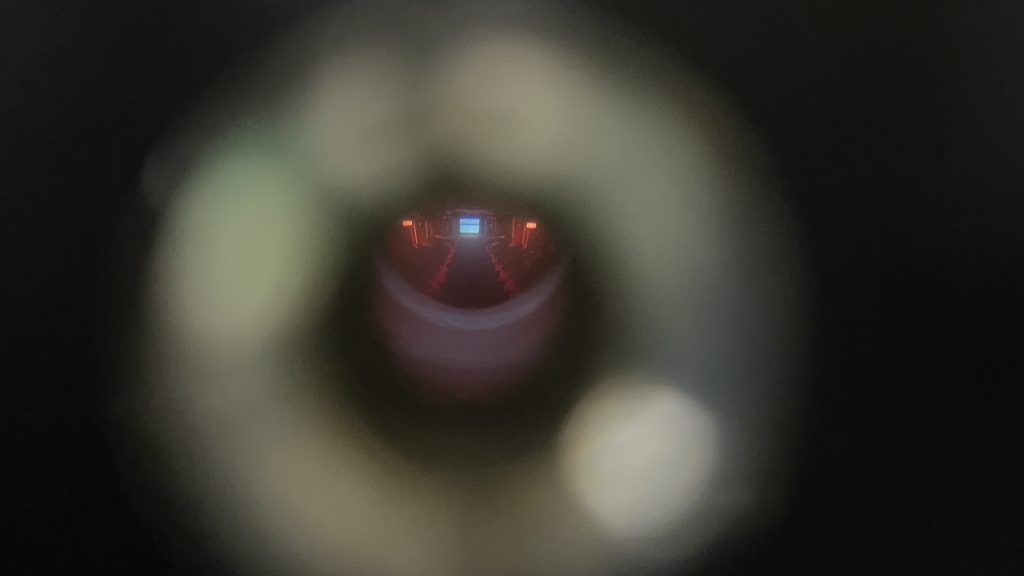-
SHARE
- X (Twitter)
《驚き盤》1975/2025年
放射状の細長い穴を開けた円盤を鏡に向けて回転させ、穴からのぞくと絵柄が動いて見える装置は、1832年にベルギーの物理学者ジョゼフ・プラトー(JosephPlateau、1801–1883)が発明し、「フェナキスティスコープ」という名称で知られている。この装置は日本では「驚き盤」として知られ、1975年に古川タクが独自に復刻した際に命名されたとされる。同年4月、東京・白樺画廊で開催された展覧会では、16台ほどの「驚き盤」装置が展示された。
「驚き盤」という名称の由来には諸説あるが、古川は1975年前後に動く絵としてのアニメーションの原理を探求し、さまざまな試みを行っていた。本祭では、プリミティブメディアアーティストである橋本典久氏の協力のもと、現存する3台の装置を複製版の円盤とともに展示する。
古川が発案した「驚き盤」装置を解析すると、絵柄円盤とスリット円盤は、異なる速度で逆回転することがわかる。これはプラトーが「フェナキスティスコープ」より前に考案した「アノーソスコープ」と類似する仕組みである。橋本は古川タク制作の装置と同じ回転比を持つ、手回しハンドルによる体験装置を作成した。
《ニッケル・オデオン・動画劇場》1988年
ニッケル・オデオンは、20世紀初期にアメリカで流行した小型の映画館である。ニッケル(5セント硬貨)1枚で入場でき、劇場内にピアノやオルガンがあり、映画にあう音楽が伴奏された。アメリカ西海岸で実際にオルガン付きの映画館を体験した古川は、のぞきからくり(ピープショー)式の装置の形で、《ニッケル・オデオン・動画劇場》を制作した。本展では、制作当時最新のブラウン管を内蔵したアナログ携帯テレビによって再生していたソフト部分を、デジタル版へ移行させるマイグレーション作業を行った。また1970年代に富士ゼロックス〈ナレッジ・イン〉(銀座ソニービル)の企画で発表した「アナモルフォーシス」の再現や檻に入った存在しない動物たちを再製作した〈Imazoo〉を発表する。
マイグレーション制作:松房子(TAKU FURUKAWA ARCHIVE)、瀧健太郎、東京都写真美術館