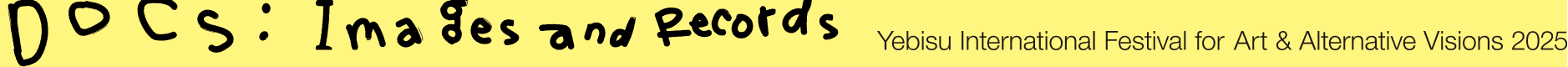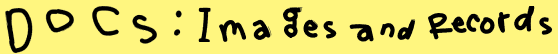-
SHARE
- X (Twitter)
STATEMENT
私は実験映画とインスタレーションを軸に、視覚と手話を中心とする人たちの生物学的な身体感覚の視点から作品制作に取り組む。近年は舞台演出も行うなど、活動の幅を広げている。
私は両耳とも聴力100dBで音の概念を持たず、日本で、アイデンティティや聴力の程度などが一人ひとり異なるろう家族※の元で育った。日本手話と日本語のバイリンガルでもある。
作品形態は上映、パフォーマンスなど異なるが、根底に共通しているコンセプトは人間の肉体と空間が醸し出す雄弁さと、その背後に存在する目に見えない抑圧の存在である。
ろう者コミュニティにあるオンガクを概念化し、音楽の定義を問うた《LISTENリッスン》、ろう者、難聴者、聴者の様々な俳優の身体の個別性と普遍性を視覚で捉える《田中家》などの無音作品を社会に発信している。その作品から生まれる現象を可視化する装置を提供することで、私たちの共通性と相違性を探り続けるとともにこの世界の社会構造を浮かび上がらせる試みを行っている。
2016年にこの時代を象徴する単語「post-truth」が流行した。「客観的な事実が重視されず、感情的な訴えが政治的に影響を与える状況」と定義され、「もう一方の事実」とも呼ばれる。技術が発達し、フェイク動画の制作が容易になった。ドキュメンタリーも、目の前にある現象を録画し制作した人の、意図に沿って作られた劇動画の一種という見方もできよう。私たちがその映像を見る時に、私たちは何をもってその映像から真実を見ているのか。
今回は、実際に西日暮里にある、私が共同運営している手話を拠点とするワーキング・プレイス「5005」を舞台にし、一回性を反復する映像と、同じ瞬間が訪れない絶対的な一回性の映像が交錯する映像自体の可能性と、その映像を見る観客と映像の間に起こる化学反応を探る。※ろう家族(デフファミリー)家族全員が耳が聞こえないこと。
ABOUT THE WORK
牧原依里《三つの時間》2025年 10分