榑沼範久プレゼンテーション ある「密度」を備えた映像・場所の準備
■持続の共存と密度
しかし、Twitterやニコニコ動画的に言葉や記号の増殖する過密状態が、どうやら僕の探している映像・場所の密度とイコールというわけでもないんですよ。「密度」とは、前回のラウンドテーブルで言えば「解像度」「本気度」あるいは「直接度」です。例えば小津安二郎監督の『東京物語』(1953)には、やはり随所に凄い密度を感じてしまいます。僕がシネフィル的リアルを共有しているからかもしれませんが、やたらとショットに打たれて心が動く。例えば、家族のひとりが亡くなったあとの場面がありますが、そのときに生じた不在は強烈な密度を持って立ち現われてきます。同じ部屋を映したショットであるために、ひとりの人間が部屋にいる/いないという差異から目を離すことができず、単純に物語の場面が悲しいということではなく、ひとりの人間が部屋にいる/いない、そして人間の周辺にある事物は絶えずそこにあるといった、映像自体のリズムというか佇まい、映像に共存している複数の持続/切断の変転に情動が激しく動かされます。
複数の持続に関連してまず参照しておきたいのは、やはりベルクソンの『持続と同時性』(1922)です。そのなかでベルクソンは、川の流れ、船の動き、鳥の飛翔、それを川岸で見ている知覚者の意識という複数の持続が統合されたり、分割され直したりする場面を描写しています。こうした多様な持続をわれわれはひとつの知覚に包括することもあるし、その全体を分割してひとつの流れは知覚の注意の外に出しておくこともできるというのです。統合や分割をすれば持続の質は変化してしまう。しかし、統合されたもの、分割されたものもまた、単純なものになってしまうのではなく、ライプニッツの「機械」のように、やはり多様な密度を保持した持続の群れです。なお、この一節はダーウィンの『生きるための闘いにおいて恵まれた品種の保存、すなわち自然淘汰による種の起源について』(1859)の終章を彷彿させます。川岸に茂る無数の異なる植物や動物が、相互にどれだけ異質でありながら、同時に相互にどれだけ複雑に依存し合っているか、それを驚きとともに川岸から眺めている知覚者をダーウィンは描写しているからです。こうした密度のある環境を、ダーウィンにしてもベルクソンにしても捉えようとしている。そして、ベルクソンはこうした密度のある環境を、統合したり分割したりする知覚の働きを強調したのだと思います。さらに辿れば、ドゥルーズは『シネマ1』(1983)のなかで、ベルクソンの『持続と同時性』をヒッチコック監督の《鳥》(1963)に繋げています。鳥たちの場所から統合された環境を分割してきた人間たち、逆に、人間たちの位置から統合された環境を分割しに襲来する鳥たち。そして、ドゥルーズは鳥的世界と人間的世界が未決定の関係に入る「休戦」状態のときに、どちらの位置から統合されたとも言えないような、持続の全体が再形成されると論じるのですが、人間的持続と鳥的持続を共存させた密度のある環境が実在するからこそ、こうした持続の分割・統合の変転を生むことができる、僕はそう言い換えておきたいと思います。
もうひとつ追加しておけば、《鳥》の3年後に刊行されたJ・J・ギブソンの『The Senses Considered as Perceptual Systems(知覚システムとしての感官)』(1966)にも、空中を飛翔する鳥の図が登場します[fig.3]。大気の流れ、空中を飛ぶ鳥の運動、そして大地の肌理とともに形成される光の流れ──鳥の視覚システムは光の流れを捉えます──が統合されて、鳥は飛翔することができる。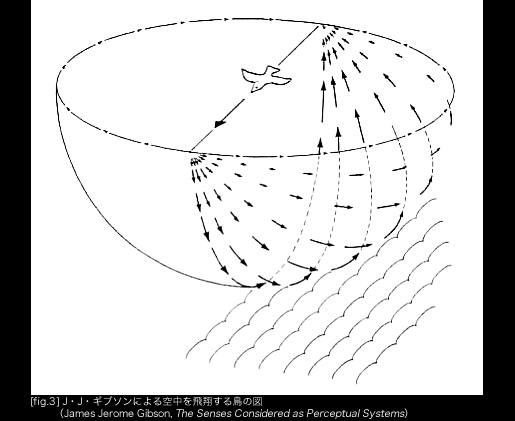
唐突に響くかもしれませんが、ここでアトリエ・ワン『空間の響き/響きの空間』(INAX出版、2009)にも登場する東京の下北沢にも触れておきたいと思います。そこでは、京王井の頭線と小田急線が交差し、多くの人が路線を乗り換えていくと同時に、駅の周囲に小劇場・雑貨屋・飲食店などが狭く曲折した街路にひしめき合う雑多な街が作られていますよね。現在、ここが再開発されようとしているわけですが、もしもあの雑多さが整理されてしまったら、あの街から醸し出される密度がおそらく失われてしまう。僕は中学・高校・大学と、京王線の調布駅から駒場東大前駅まで通っていたので、下北沢で乗り換える必要はないのですが、とくに中学・高校時代は学校の帰りに下北沢でよく途中下車しては街を歩いていました。今から考えれば、違う意味で「乗り換え」をしていたのだと思うんですね。学校空間からの「乗り換え」です。生まれ育った調布もまた、複雑な構成要素を抱えた場所でした。フラットな郊外ではなく、武蔵野の雑木林、寺、神社、湧水の出る湿地、川、植物園、住宅地、天文台、航空研究所、米軍飛行場跡地などが点在している混成空間です。水木しげるさんも住んでいる(笑)。
ひとつの建築もまた、こうした混成的な場所の密度を孕むことはできないでしょうか。藤本壮介さんの『原初的な未来の建築』(同、2008)を読んでいたら、「密度」という言葉が頻出する部分を見つけました。建築自体を「密度」から分析するのは今後の課題になってしまいます。今日は言葉だけでも紹介しておきたい。「建築というのは、その始まりにさかのぼって考えると、さまざまな密度の濃淡による『ぼんやりとした領域』なのではないだろうか。内と外とは、場の密度の違いに過ぎない。家と街は、同じものの違った現われとなる」(74頁)。「都市のなかのかすかな密度の高まり。グラデーション」(76頁)。「砂漠の真ん中に人は住めない。純粋な空虚は、住むための場所ではない。──emptiness。単なる高密度には人は住めない。圧迫される不快な密度は住むための場所ではない。──density」(82頁)。「ポジティヴな高密度」(83頁)。「落ち葉が集まったように、かすかに場所の密度が作られる。その密度の起伏を、さまざまに読み取り使いこなしていく」(86頁)。映像における「ポジティヴな高密度」も探っていかなければなりません。
■映像の誘発力
ここでもう一度、ゲームやニコニコ動画に話題を戻します。大学院生時代、蓮實重彦先生の授業でこういうやりとりがあったのを思い出しました。文脈は忘れてしまったのですが、あるとき蓮實さんが、あの深い声でこう断言したんですよ。「映画はリアルですが、テレビはそうではないでしょう」。シネフィルらしい学生たちは頷いていました。けれども、僕の友人で、ジャック・ラカンの精神分析を研究していた松本展明が、甲高い声でこう訊いたのですね。「あのー、どういう意味でリアルとおっしゃっているのか教えていただけませんか」。すると蓮實さんは確か、こういう感じに答えたんですね。「例えば、あなたのその取り憑くような甲高い声、私は好きではありませんがリアルでしょう」。ここで「映画はリアルですが、テレビはそうではないでしょう」という蓮實さんの言葉を変奏してみようと思います。「ゲームやニコニコ動画はリアルですが、映画やテレビはそうではないでしょう」。ゲーマーやニコニコ動画にハマっている人ならば、そう断言するかもしれませんよね。僕はゲームやニコニコ動画こそが、本当のリアルだと言いたいわけではありません。しかし、「映画やテレビには反応できないから」、「映画やテレビには自分のコメントが書き込めないから」、「映画館ではずっと暗闇の座席に縛られていて、歩き回ることもできないから」リアルではない。そう断言する人がたくさんいて、シネフィルの共同体と同様に、何かしらの説得力を内部で持つ共同体が形成されることだってありうるのではないですか。
もちろん映画初期には、画面に対して反応を返そうとする人々もいたはずです。しかし、暗闇に身を沈め、すべての映像を網膜と鼓膜でひたすら受け止めようとするシネフィル的リアルのあり方が、どうも登場するようになった。これは『物質と記憶』(1896)のベルクソンを援用しながらドゥルーズが映画史に位置づけた、「運動イメージの危機」と関係があるのではないでしょうか。知覚と行動を結ぶ感覚-運動図式が緩んだり、崩れたりする事態ですね。するとイメージを行動に延長することなく、過剰なイメージを受け止める登場人物が前面に出てきます。映画作家としては、まず小津安二郎、ロベルト・ロッセリーニを取り上げている。時代は下りますが、デヴィッド・リンチをそこに入れることもできると思います。こうした「運動イメージの危機」が画中の人物において生じるのではなく、観客と画面の関係において生じると、それがシネフィル的リアルになるのではないか。
もっとも、こうした効果は20世紀初頭からすでに生じていたはずです。前回に柳澤さんもベンヤミンの『複製技術時代の芸術作品』を引用されていましたよね。映画の場面がどんどん切り替わっていくとき、映像に距離を取ることもできないままにどんどん触覚的体験のように押し寄せてくる。こうした「ショック経験」は、自分の知覚したものと、それを行動に延長できないというズレから生じるのではないでしょうか。そうだとすれば、ショックを受け続けることを避けて、体内のホメオスタシスを達成しようとするならば、映像に何らかの所作(behavior)をインタラクティヴに返してやる必要があるはずです。ベンヤミンによれば、歴史の転換期においては、人間の知覚器官が技術の変化にともなう課題に直面するともいいます。そうした課題を視覚だけで解決することはできず、触覚的な受容や慣れを通して、だんだんと解消されていくという指摘もありました。映像に対する身体の所作、インタラクティヴィティ、あるいは触覚的な受容や慣れを、この文脈で考えてみることができるはずです。
自作の水上スキーに乗って映画を撮影していたフレッド・ウォーラーは、第二次世界大戦期になるとアメリカ軍の要請を受けて、インタラクティヴな射撃シミュレーター「Gunnery Trainer」を開発します。波状のように押し寄せる映像から、所作誘発的なインタラクティヴ映像への転換です。さらにウォーラーは戦後、巨大な3面プロジェクション・システムを開発し、それを駆使した「CINERAMA」を公開します[fig.4]。ギブソンもこれを知覚研究に活用できないかと、ウォーラーに宛てた手紙を書いているんですよ。「CINERAMA」はインタラクティヴではありませんが、まるで建築空間を動きながら経験するように、映画の画面のなかに観客を包囲しようとした装置でした。
インタラクティヴな映像ということで世代的に外せないのは、やはりテレビゲームです。先程、下北沢を少し話題にしましたが、中学2年の頃はテニスにもはまりながら、同時に下北沢のゲームセンターにも通っていたんですね……。そもそも小学校高学年のときに、1978年に「スペースインベーダー」が大流行して、下手くそながら親指が痛くなるまでボタンを押し続けました。自分が真剣に映画を観るようになる前のことです。「ディグダグ」は中学生になってから登場したので、下北沢のゲームセンターでハマったゲームのひとつはこれです。ディグダグをしたあとは、電車に乗って帰宅する途中もディグダグのことばかり考えていて、どうも駅で直角に歩いてしまう(笑)。同時代性を帯びていると思うのですが、1976年にはピンクレディーが「ペッパー警部」でデビューします。モーニング娘。も2008年にカバーした曲ですね。このときに多くの子どもたちが、テレビに映るピンクレディーの振りつけの真似をし始め、感染するように広がっていきました。それから、ピンクレディーと同じ時期に活躍した映像作家にナム・ジュン・パイクがいます。なぜ彼は《Magnet TV》(1965)において、テレビに磁石を近づけて画面を歪ませたのか。なぜ彼は《Concerto for TV cello》(1976)において、テレビの画面をチェロに見立てて弾くような作品を構想したのか。それはテレビから大量に押し寄せてくる映像に対して、インタラクティヴに所作によって、触覚性によって反応を返そうとしたからに違いありません。人間の知覚器官が技術の変化にともなう課題に直面したとき、どのようにしてこの課題を解消しようとするのかというベンヤミンの指摘が活きてきます。
もうひとつ、テクノグループのアンダーワールドも挙げておこうと思います。ロンドンのブリクストンや千葉の幕張で彼らのコンサートに行ったことがあります。大音量の電子音というか念仏というか、その反復とともに、目まぐるしく入れ替わる抽象図形や映像や文字や多色の光がVJ的に巨大スクリーンに投影されて流れていきます。DVD『Everything, Everything』(2000)ならばなおさらなのですが、画面が多重レイヤーになっていて刺激の過密状態です。しかしヴォーカリストのカール・ハイドが、その前で独特の下手くそな踊りをしている。ただ単に下手なのではなくて、観客の踊りを誘発するんですよ。煽るように踊るヴォーカリストに対して観客全員が反応している。なぜ、こんなに多くの観客が所作を誘発されるのか興味深い。ピンクレディーも凄くないわけではないけれど、圧倒的な技術で踊るわけではないから真似を誘発するのでしょう。「すごくない」と「すごい」の中間あたりに、「模倣の谷」というか「模倣の山」があるのかもしれません。ただ、知覚器官が過剰な刺激に直面していているという状況もポイントではないのかと。ナム・ジュン・パイクもピンクレディー現象もテレビゲームも、テレビの普及によって知覚器官が被った歴史的課題への応答だと考えられるからです。ニコニコ動画を覗きながら、こうしたことが頭に浮かびました。プレゼンテーションを終わります。