榑沼範久プレゼンテーション ある「密度」を備えた映像・場所の準備
■質疑応答 3
柳澤
とても面白く拝聴しました。確認的な質問になるのですが、お話の大きな主題は、前回の議論のなかでも問題となった、古くはプラトンの「洞窟の比喩」に遡る、虚と実が曖昧で、場合によっては虚実がいくらでも入れ替わっていくわれわれの知覚世界の問題だと理解しました。ただそのときに、虚と実を分ける根拠をどこに持ってくるかは、立場が分かれると思います。榑沼さんのお話では、共同主観性、仲間的な主観性が言及されていました。榑沼さんはおそらく、その虚実の線引きが、時代的にもかなり変化していくという前提をお持ちだと思うのですが、その場合私たちの身体的な知覚に拠って立つことが即リアリティ=実在になるのではなく、あくまでも歴史的に共同主観性がいわば事後的に虚と実を決定していくということになるのでしょうか。
榑沼
身体と直接接触する実在の水準まで、歴史決定、歴史構築を考えているわけではありません。「何をリアルと感じるのかを言う」という水準で、今回は歴史性を探りたいと思いました。繰り返しになりますが、ロボットの制作で言えば、ロボットに心が本当にあるかどうかは別として、さらに言えば、われわれ人間に心が本当にあるかどうかは別として、われわれの生活のなかで心という設定が機能するかどうかが重要ではないかと。設定が機能しているというのは、「ロボットに心があるとリアルに思えてしまう」、「だから人間と同じようにロボットとコミュニケーションして不自然に感じない」という状態です。ただし、心があるとリアルに思わせる感情システムは実在していると思っていますし、虚と実を振り分けるメカニズムも実在していると思っています。
「実在」という言葉で思い出したのですが、大学院生の頃、ある夏の晴れた土曜日の朝、知人が久しぶりに電話をしてきたことがありました。そして、唐突に「榑沼さんは実在を信じますか」と切り出しました。いわゆる哲学問題として訊いているのか、それとも相当に切迫した問題として訊いているのか。それをまず知人として知りたかったのですね。彼はこのように答えたと記憶しています。「こうして話をしている榑沼さんの声が実在していると僕は思っていません」。僕はそのとき、すごく怖かったですよ。電話口で話している自分の、この声が実在していないと言われたわけです。電話口がブラックホールになって、実在なるものが吸い込まれるような感覚がしました。僕の主観性の地平から相手の主観性の地平に大逆転が起きて、しかもそれが実在しないと宣言されてしまった。前回の平倉さんの話にあった、ないはずの砲台の攻撃によって自分が殺されうるというウィトゲンシュタインの経験にも関係するはずです。そこでは自分の主観性の認識論的な閉域が破られるわけです。ですが、先週からロボットのことを考えつつ気づいたのですが、次のように言われたとしてもそれほど怖くないのではないでしょうか。「榑沼さんは心の実在を信じますか。こうして話をしている榑沼さんの心が実在していると僕は思っていません」。実在やリアルにも多様な水準があるはずです。
大橋
僕は榑沼さんが提出されたお題を、だいたい次のように考えてみました。人ははじめにリアルな所与があったとして、まずそれを取り入れる。そこで、概念でもカテゴリーでもいいのですが、要はある仕方で何かの経験を振り分けていくようなグリッドを作る。ところが、ひとたびそのグリッドができてしまえば、あらゆる経験がそのグリッドに則るようにしか見えてこない、という傾向があるのではないか。で、榑沼さんはこうしたグリッド形成のモメントを追いかけたいのではないかと思ったわけです。例えば、体の動きが一度ピンクレディー的なモードとして入ってきてしまうと、次からは似たような動きも全部ピンクレディーに見えてしまって、ピンクレディーのものまねがしやすくなったり、「ピンクレディー」的な動きが巷にあふれるということになる。あるいは榑沼さんの発言がTwitterに還元されないということも、同じことかもしれません。
Twitterに乗らないということ自体が、榑沼さんの用語体系が彼らのヴォキャブラリーにはなかったものだということを示している。メディア以前に、選択するフィルターとしての「彼ら」がいるわけです。彼らは彼ら固有の言語体系、僕のさっきの言い方ですと「グリッド」をもっていて、そこに乗らないものは認識されない。このようにして、いったんメディア環境や世代環境のなかであるグリッドができてしまうと、どうにも漏れてしまうものが生じてくる。ひょっとしたら榑沼さんはそのことを遺憾に思っているのかな、と思いました。そうして、そんな構造自体に棹さすために「ネタフィジックス」とあえて言ってみたりしているのかな、とも思いました。
榑沼
僕が「ネタフィジックス」という言葉を発したのは公開講座の最中のことで、Twitterでの記録を読む前のことですから、「ネタフィジックス」と「ツイート(笑)」「ツイート(ニコニコ)」は関係ないです(笑)。むしろ、複雑な社会的現象を明快に解読してみせるという「社会学的構え」に傲慢さと退屈さを感じてしまうことがあり、その感情が「ネタフィジックス」という揶揄にもなったんですね。
ところで、大橋さんのお話になったグリッドに関してですが、ひとつ留保しておくならば、僕は言語というグリッドによって知覚世界すべてが分節されているとは考えていません。名付けられないものはたくさんありますし、世界の無数の階調は言語システムではなく知覚システムによって接触可能です。それに直面して動くこともできます。肉体のメカニズム、生態的作動の条件も含めてグリッドというならば、われわれは複数の水準のグリッドが折りたたまれた「機械」なのでしょう。「自然の機械、つまり生物の体は、それを無限に分けていってどんな小さな部分になっても、やはり機械なのである」とライプニッツが『モナドロジー』(1714)のなかで言うような「機械」です。だから、グリッドの外があると僕は考えていませんし、グリッドという洞窟の外に出ることがわれわれの求めていることだとも考えていません。言語化されない残余が「現実界」であり、その「現実界」を欲望するという言説は、症例としては切迫していたとしても、そうではない哲学問題としては疑似問題ではないでしょうか。
大橋
補足しておくならば、僕の言う「グリッド」は、単純な意味での言語ではなく、広い意味での言語も含めた知覚の形式、あるいは知覚された所与を前意識的にグルーピングしたり腑分けしたりする「全-形式」、ないしはゲシュタルトのことです。カント的に言うならば、悟性概念の成立以前にある「超越論的図式」のようなものですね。で、話を戻すと、今のネットコミュニティのような場所では、非常に狭いグリッドが幅を利かせているのは、まずもう間違いがないわけです。別にそれを「ジャルゴン」と呼ぼうが、「党派性」と呼ぼうがかまわないけれど、逆にそうした言葉遣いが、今度は現実の認識を固定してくる。例えば「アーキテクチャ」議論のように。お話をうかがいますと、こうした状況に対して、ひょっとして榑沼さんは、50%程度の挑発性をもって、異議を申し立てているのではないか、と思った次第です。
榑沼
ええ。ただ、僕はTwitterのアーキテクチャ、ニコニコ動画のアーキテクチャ自体の善し悪しを言っているわけではないんですよ。僕も意外に新しいもの好きですから、むしろあれをどう使えるのかに関心があります。
大橋
そうなると、せっかく新しいものを使っているのに一体何をやっているんだ、という怒りですかね(笑)。
榑沼
「ある密度」をどうすれば作れるのだろうと考えていますし、それこそドミニクさんはそれを作り出そうとしているではないかと期待しています。
ドミニク
そこに絡めての質問なのですが、インタラクティヴ技術を指して、映像経験にはアウラが消滅する、あるいは蒸発するといったことをおっしゃっていた。そこが論理的にどう繋がるのかがわからなかったので、もう少し伺いたい。
榑沼
手工業的な複製ではなく、機械技術による複製を主題にしたベンヤミンの『複製技術時代の芸術作品』ですが、そこにはアウラがいろいろな姿で出てきたように記憶しています。メディア環境とは関係なく語っているようなところもある。例えばアウラは、夏の昼下がり、木の下に寝そべりながら山の稜線を眺めているときに現われる。そこでは遠くにあるけれど近いような、近いようなものが遠くにあるような、そういう距離の撹乱が起こる。僕はそうした距離の撹乱が何によって生じるのか、つまりアウラが作られる条件とは何なのかに興味があります。ファシズムへの抵抗、そしてアウラが消失する複製技術の条件がこのエッセイの主題でしょう。そのうえで今、僕が気になるのは、そもそもアウラはどう形成されるのかということなんですね。機械技術によって複製される前、芸術作品は礼拝的価値によってアウラを宿していると言われても、なるほどとは思えないわけで、そもそも、複製されないどの作品にもアウラが宿るなんてことはないでしょう。むしろ、アウラが形成される条件をもっと詰めて考えてみたいのですね。アウラという言葉も混合物だと思いますが、ここでは距離の撹乱をひとつの条件として挙げてみたいと思いました。前回、レンブラントやリンチを取り上げながら柳澤さんが報告されたことと、つながるのではないでしょうか。身体による探索行為の可能性が「編集」によってカットされ、身体と事物との関係に揺らぎが生じる。あるいは、心理学者デビット・カッツのフィルム・カラーのように、身体との関係が縮減されて、距離感覚に攪乱が生じる。それがすべてではありませんが、アウラが形成されるひとつの条件として考えられるのではないでしょうか。外界を感覚によって受け止め、それを運動に延長していく感覚-運動回路が緩む、切断される「運動イメージの危機」によって、アウラのひとつが生じるのではないか。
逆にベンヤミンの言うアウラの消滅についてですが、僕はこれが技術的複製では決定的に生じなかったと思うんですよ。ベンヤミン自身にしても、ソヴィエト映画によって新しい顔の映像が登場したと言うとき、その得体の知れない顔の出現はアウラとも受け取れる。また、バルトが写真について記したプンクトゥムにしても、シネフィル的なリアルにしても、アウラが消滅しなかった証拠ではないでしょうか。少なくとも、アウラの存在がひとりの幻想としてではなく、共同主観的に共有されたところはある。アウラが蒸発したり希薄化したりするとすれば、むしろ「運動イメージの危機」が所作誘発性技術によって解消されることに関連しているのではないか。所作誘発によるアウラの消滅を、けっしてネガティヴに語っているわけではありません。何か違う映像のありかたにつながる可能性もあるはずです。前回に平倉さんが語っていたような、暗闇で視聴覚ショックを与えられる現在までの映画館とは違ったかたちの映像環境、動き回りながら本気になるような映像環境もそのひとつでしょうか。
ドミニク
いろいろなテーマがありましたが、僕なりに思ったことをポイントとして残しておきます。最初に「本気になる」という話があって、そのあとにメタフィジックスと「ネタフィジックス」の往来がありました。おそらく身体がすぐ動物的に反応してしまう次元と、思考が反応してしまう次元というものがネタとメタだと思いました。その後に藤本壮介さんの話があって、そこでは解像度の中間層をどう作るのかという話をされていた。幾度となく繰り返される所作や感情の誘発力とは、J・J・ギブソン的な系譜でいうと、ギブソンより前の心理学者クルト・レヴィンのインヴィテーション・キャラクター(Aufforderungscharakter)というアフォーダンスより強い概念があって、それが人間のコミュニケーションを駆動しているというのは、非常に本質的な話なのかなと思いました。おそらく、心の理論であったり、ミラーニューロンの話であったり、ニコニコ動画もTwitterも、強いて言えばあらゆるウェブ・メディアというものは、ユーザーとの距離を撹乱させるという意味でのユーザーの鏡像が投影され、そこでひとつの作動系が発生する。
距離の錯乱との関係でいうと、僕は剣道をやっていたのですが、「遠山の見付け」というものがあって、遠くの山を見るように自分の目の前の敵を見る、というものです。禅問答的なのですが、それは自己対他という二項対立を超える話だと今は理解していますが、それを身体的に実践するのはなかなか難しい。
いろいろなテーマがありましたが、僕なりに思ったことをポイントとして残しておきます。最初に「本気になる」という話があって、そのあとにメタフィジックスと「ネタフィジックス」の往来がありました。おそらく身体がすぐ動物的に反応してしまう次元と、思考が反応してしまう次元というものがネタとメタだと思いました。その後に藤本壮介さんの話があって、そこでは解像度の中間層をどう作るのかという話をされていた。幾度となく繰り返される所作や感情の誘発力とは、J・J・ギブソン的な系譜でいうと、ギブソンより前の心理学者クルト・レヴィンのインヴィテーション・キャラクター(Aufforderungscharakter)というアフォーダンスより強い概念があって、それが人間のコミュニケーションを駆動しているというのは、非常に本質的な話なのかなと思いました。おそらく、心の理論であったり、ミラーニューロンの話であったり、ニコニコ動画もTwitterも、強いて言えばあらゆるウェブ・メディアというものは、ユーザーとの距離を撹乱させるという意味でのユーザーの鏡像が投影され、そこでひとつの作動系が発生する。
距離の錯乱との関係でいうと、僕は剣道をやっていたのですが、「遠山の見付け」というものがあって、遠くの山を見るように自分の目の前の敵を見る、というものです。禅問答的なのですが、それは自己対他という二項対立を超える話だと今は理解していますが、それを身体的に実践するのはなかなか難しい。
榑沼
自己と他の二項対立を超えるというのは、もうひとつの流れに入るということだと思います。3という複数性がどうも重要なのではないか。ベルクソンの『持続と同時性』を援用したドゥルーズの『シネマ1』も、ヒッチコックの《鳥》を素材にしながら、やはり3つの流れ、3つの持続が合流したり分割されたりする、3つ組の密度を鍵にしていますよね。僕の祖父が範士だったからかもしれませんが、ドミニクさんの剣道の話はすごく響くものがありました。
大橋
距離の撹乱という観点から、僕もひとつ参照項を出しておきたく思いました。カルロ・ギンズブルグという歴史家の考察です。ギンズブルクは「中国人官吏を殺すこと」という小論のなかでディドロの議論を参照し、ヨーロッパにいる身から考えるならば、中国で中国人の官僚を殺すこと、あるいはそれを想像することは、道徳的に痛くも痒くもないし、いかなる疚しさの感情も引き起こさないだろうと言っている。つまり、距離とは道徳感覚を麻痺させるものだ、というわけです。ギンズブルグはディドロを解釈しつつ、モニター越しにミサイル発射のボタンを押して人を殺す時代のことを考えています。そう考えると、距離の撹乱と一言で言っても、そこにはなかなか人をぞっとさせる部分もあるのではないでしょうか。
ドミニク
僕は大学生の頃に、ネットゲームでテロリストをバンバン撃って殺していたわけです(笑)。一晩中そういう経験をして、渋谷のセンター街を朝日を浴びながら歩いていると、センター街のいろいろなビルから自分が狙われているような感覚に襲われます。これは以前、日本だと精神医学の中井久夫さんが『批評空間』でおっしゃっていることですが、ヴェトナム戦争中のアメリカ軍がジャングルのなかで敵兵に遭遇する。あるとき発砲率を測定すると10%くらいだったそうですが、練習用の麦わらのボディーの中にトマト缶を入れて、それを撃つと血が飛び出るという練習を反復させた兵士は40%くらいまで上がったそうです。おそらくゲームだけではなくあらゆるメディア、映画を観て、ドラマを観て、ゲームをして、小説を読んで、そうした妄想するなかで人を撃ったりミサイルを撃ったりすることは、全部ある程度の強度を持った「実」だと思う。おそらく僕が銃を持たされて撃ってみろと言われたら、ネットゲームをやっていない人に比べて発砲率がすごく高いと思う。でもそれがそのまま僕の倫理観が崩れているということにはならないとも思います。そういう複雑な相関のなかで、僕が撃つことは決定されている。
そういうこととも絡めて、インタラクティヴな映像体験においてアウラが降りない、あるいは降りるということは僕はちょっと理解できない。ですから、蓮實さんの「映画vs.テレビ」という基準線は、僕はちょっとナンセンスだなと感じてしまいます。というのは、僕は映画にも強度を感じることができるし、また1981年生まれなので、ちょうど映画も高度化し、ゲームも発達していたので、両方ともリアルなのです。たぶんそうした時代区分的なところが大きいのではないかと思います。
榑沼
シネフィル的リアルとドミニクさんの言うリアルは同じではないですよね。このあたりは、またあとの議論でつながっていくことになるかと思います。
平倉
3つの持続が作り出すものが「ある密度」であるというお話がありましたが、もっと多くの持続が同時にあるのではないかと私は思っています。その点で、ドミニクさんのおっしゃる「遠山の見付け」の話は興味深い。何かを意識的に見ようとすると、せいぜい1つか2つの場所に意識が集中してしまうわけですが、焦点を少し遠くに持っていくと、全体がある種のパターンとして現われてくる。そうして同時に複数の出来事に対して身構えるような体勢がとれるようになる。そういう複数性の場を、中間層という言葉と繋げられていたのが面白かった。
藤本壮介さんのテクストでは、この中間層のことを「曖昧」と呼んでいるのだと思います。ただ、私はこの「曖昧」という言葉に少なからぬ違和感を覚えます。虚と実を立ててその中間に曖昧なグラデーションを作るという、そういうかたちで問題を考えていいのか。遠い・近い・その中間、という話ではなくて、近いものを遠くを見るようにして見たときに、ものの見え方自体が内側から複数に分裂してくるような事態が考えられなければならないし、それは少しも曖昧なことではない。グラデーションで考えると、砂漠では住めない、高密度では住めない、適度に過ごしやすい中間的な場所に住もう、という話になってしまいますが、当然ながら砂漠に住む人はいるし、高密度な場所に住むことを好む人はいる。二項を立ててその中間を取るというやり方は、そういう意味では、住むことの複雑なリアリティから離れてしまう。もちろん藤本さんは建築家ですから、実際に設計するときは違う仕方で問題を解いているのだとは思いますが。ともあれ「ある密度」という言葉の「ある」の部分の複雑性を内側から分析する方法を、二項の中間を取り出すという方法ではない仕方で思考すべきだと思います。
ドミニク
榑沼さんの「模倣の谷」という言葉にピンときたところがあります。アンダーワールドのヴォーカルのヘタクソなダンスやピンクレディーのダンスの話でしたが、これはゲームの世界でも最近よく話題になります。「ファイナルファンタジー」というゲームはそのモデルを映画というまさにオールドメディアに求めたインタラクティヴ・ゲームで、僕は「I」からずっとやっているのですが、個人的には後続のシリーズ作になるほどどんどん愛情が薄れている。そこに非常に問題意識を抱えています。ファミコン時代の、いわゆるローレゾリューションの、256色しか表現できない、音源も16音しかないような頃のファイナルファンタジーの体験の記憶を喚起するときと、今のハリウッド化されたファイナルファンタジーを比較すると、僕のなかの「模倣の谷」は明らかに昔のファイナルファンタジーに反応している。というか反応できている。つまりアフォーダンスがあるわけです。最近の高解像度になった、映像だけをひたすら与えられるようなファイナルファンタジーでは、なかなか自分との距離が計りづらい。これは距離の撹乱というより、距離の消失と言ったほうが近いかもしれません。与えられた情報が低解像度であることと、感情誘発力や所作誘発力が高いこととにはなにかしらの比例関係があるように思います。
榑沼
グラデーションという曖昧な中間を考えていたのでは、「ある密度」の「ある」を把握し損ねてしまうという平倉さんの指摘に考えさせられました。これは石黒さんの『ロボットとは何か──人の心を映す鏡』(講談社現代新書、2009)に出てくる概念図なのですが、X軸が人間に似ている度合い、Y軸が親近感になります[fig.5]。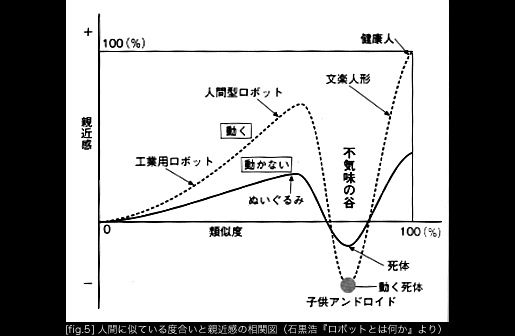
ロボットが人間に近づくにつれて親近感も上がるのですが、100%の手前で一度親近感がガクンと落ちる。石黒さんはこれを「不気味の谷」と呼んでいます。では、この「谷」で何が生じているのか。グラフ上では類似性のグラデーションの中間ですが、人間の知覚において生じていることは、人間/非人間を区分する認識システムの活性化ではないかと石黒さんは予想するのですね。人間にあまり似ていなければ、人間/非人間の差異に敏感になる必要はありません。僅かの差であっても人間/非人間をぎりぎりのところで区分させる地帯、その区分に敏感にならざるをえない地帯、その区分がにわかに決定しにくい地帯。それこそが「不気味の谷」の真相でしょう。似たようなことは、ダーウィンの『植物の受精』(1876)で論じられている個体差の程度と生殖可能性との関係についても言えそうです。配偶者どうしの性的要素の個体差の度合いを軸にすると、稔性と不稔性にはグラデーションがあって、両端では完全に生殖可能性がゼロになる。個体差が過度でも不十分でない中間層に生殖可能性のゾーンがあるというのですが、「生殖性の山」で生じていることは、とても曖昧ではないジャストな遭遇ですから。ここから平倉さんのプレゼンテーションに移りたいと思います。